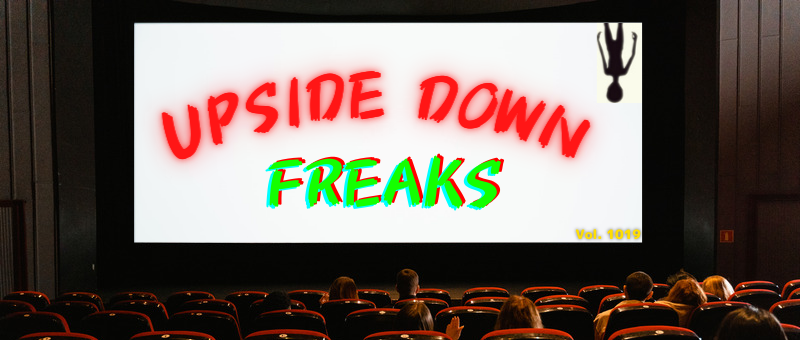何を見せられてるのだろう
ウィッカーマン
サターン・フィルムズ
エメット/フルラ・フィルムズ
エクイティ・ピクチャーズ
ほのぼの感想&解説
オリジナルは1973年に映画化されている。
「wicker man」という言葉は編んで作った人形を意味する。
ウィッカーマンとは、キリスト教が普及する前の紀元前に、ケルト人が信仰していたドルイド教における、人間や家畜を巨大な人形の中に閉じ込め火炙りにする儀式である。
公開当時は酷評の嵐であったが、今ではニコラス・ケイジの演技のおかげでカルト映画となっている本作。
その年の最低映画を決める第27回ゴールデンラズベリー賞では、見事5部門にノミネートされた。
最低作品賞
最低男優賞:ニコラス・ケイジ
最低スクリーンカップル賞:ニコラス・ケイジ&彼のクマのスーツ
最低リメイク及び盗作賞
最低脚本賞:ニール・ラビュート
『マッド・マックス』に憧れているかのような格好の冒頭ケイジ。
いつものようにパトロールをしていると、前方を走る車からぬいぐるみが落っこちた。
拾い上げ、渡すと、再び女の子がぬいぐるみを道路に投げた。
それを拾っている間に、母娘が乗る車に大型トラックが突っ込んできた。
燃え盛る車から何とか救出を試みるも、爆発の勢いで吹き飛ばされ救うことができなかった。
それがトラウマとなり幻覚に襲われるケイジは、警察業をしばらく休むのであった。
しかし突然姿を消した婚約者から行方不明になった娘を探してほしいという自分勝手な手紙が届き、心優しいケイジは思い立って彼女たちが暮らす孤島に向かった。
その島は女性が絶対的権力を持っており、男性は少数で力仕事をさせられている。
娘の通う学校に出向くも、先生にも生徒たちにも小馬鹿にされる始末。
ケイジの憤りが溜まる。
この島には養蜂場があり、蜂がキーポイントになりそうな予感をさせておくのだが、ただ単にケイジに対する拷問道具としての意味しか果たさない。
さすがのケイジも蜂には翻弄される。
『シャイニング』(1980)を彷彿とさせるケイジの幻覚カットを挿入してくる。
再び蜂。
いつからか、ケイジのトラウマは母娘の自動車事故よりも蜂に切り替わっていたのだ。
幼い女の子を生贄にする儀式の詳細を知ったニコラス・B・ケイジは、怒り狂い女性相手にパンチとハイキックをお見舞いする。
ニコラス・ケイ史に新たな歴史が加わった。
ヒーロー的に描かれた警察官の主人公が、女性に暴力を振るうなんて前代未聞だ。
しかしながら映画として、かつケイジとしては、コメディチックなアクションシーンに笑いが止まらない。
儀式にはヘンテコな仮装での出席が必要なんですね。
『ブレイブハート』(1995)かよ!
ケイジは熊かい!!
仮装が甘くすぐにバレてしまい、近づいてくる輩に銃で脅すも、弾はすでに抜かれていた。
実は、真の生贄はケイジだったのだ。
毎年女の子を犠牲にしていたのだが、今年は不作だったらしく、試しに男を生贄にしてみることに委員会で決まったらしい。
そこで選ばれたのがケイジ。
娘の行方不明も嘘で、婚約者の仕掛けた餌だった。
先ほどキックされたので、仕返しとしてハンマーで足を砕かれるケイジ。
「脚がぁぁぁぁぁああぁぁ~!!脚がぁぁぁぁぁああ~!!」
痛い部分の名称を叫ぶケイジ。
いい気味だ。
そして伝説のシーン。
蜂をぶち込まれます。
「ハチ!ハチ!!ハチィ~~~!!!」
目に見える虫の名称を叫ぶケイジ。
「目がぁぁあぁあっぁぁ目がぁぁぁあぁあぁ~」
とにかく痛い部分の名称を叫び散らすケイジ。
真面目に演じる気がもはやなくなったのか、コントのような手抜きっぷり。
いまやお得意芸。
しかしこの蜂の拷問シーン…劇場公開版ではカットされています。
カットすべき判断基準が私にはわかり兼ねます。
ハッピーエンドですね。
巨大わら人形の頭の部分にケイジ閉じ込められてます。
火をつけたのは実の娘と思いこんでいた女の子です。
結局実の娘だったのか、そうではなかったのかよく覚えてません。
しかしながらケイジを生贄にしたところで豊作になるとは思えません。
明日自慢できるトリビア
魅惑の深海コーナー
バーニングマン
起源は1986年、カリフォルニア州にて仲間内で木製人形を燃やしたことに始まり、
現在はアメリカ・ネバダ州のブラックロック砂漠で、毎年8月の最終月曜日から9月の第一月曜日(米国の祝日「レイバー・デイ」)まで開催されている『バーニングマン』という行事がある。
約5、6万人が参加する。
最終日に“ザ・マン”と呼ばれる巨大な木製の像を燃やす。
10か条だけ定められており、基本的に自由である。
『どんな者をも受け入れる共同体である』
『与えることを喜びとする』
物々交換ではなく、料理を分け与えたり、娯楽場所の提供など、条件なしで与えること。
『商業主義とは決別する』
企業の宣伝やメーカー名は隠した方がいい。
金銭のやり取りは基本的に禁止。
主催者側が用意した飲料水や氷は購入できる。
『他人の力をあてにしない』
1週間分の水と食料は全て自分で用意すること。
『本来のあなたを表現する』
傍観者では許されないので参加すること。
普通の恰好で行くのは論外。
全裸の人もあちこちにいる。
『隣人と協力する』
『法に従い、市民としての責任を果たす』
『跡は何も残さない』
ゴミは全て持ち帰る。
『積極的に社会に参加する』
『「いま」を全力で生きる』