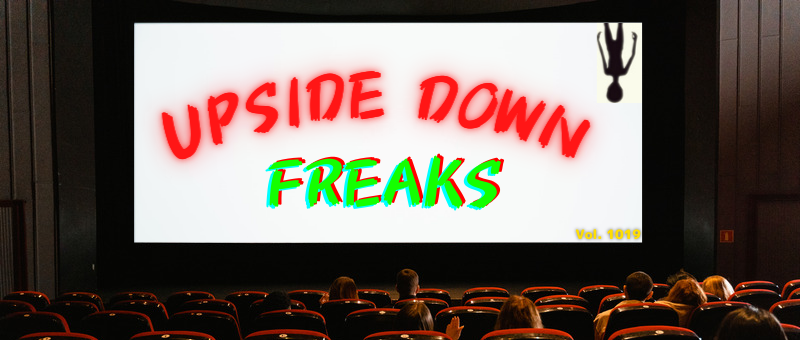ツッコみながら見ているといつの間にか人類が支配されてました。
吸血鬼ゴケミドロ
佐藤友美
北村英三
高橋昌也
高英男
加藤和夫
金子信雄
楠侑子
山本紀彦
キャシー・ホーラン
小林久三
一言粗筋
ほのぼの感想あるいは解説
本作は『宇宙大怪獣ギララ』(1967)の翌年に、松竹特撮映画第2弾として公開された。
羽田空港から伊丹空港に向かう途中、空が赤く染まり始め、鳥が窓に衝突してくる異常事態発生。
この赤い空の風景は、クエンティン・タランティーノが『キル・ビル Vol.1』(2003)でオマージュを捧げている。
管制塔からパイロットに、この飛行機に時限爆弾を持って潜んでいる者がいるという連絡が入る。
進路を変更した羽田に戻ることに。
機内では一人一人に荷物検査を行う。
結構適当にしているのだが意味はあるのだろうか。
そんな中、別の問題が発生。
大使を暗殺し、逃亡したテロリストがこの飛行機には乗っていたのだ。
彼にハイジャックされる。
そしてさらなる問題が発生。
突然パイロット席の目の前にオレンジ色に光り輝くと空飛ぶ円盤が出現。
そして墜落。
不時着して生き残ったのはわずか10名。
辺りは砂漠でどこなのかもわからない状態。
生き残った人物
①男性副操縦士と②女性キャビンアテンダント
③政治家、その④側近、そしてその⑤妻
政治家と側近の妻は不倫関係。
機内では隣同士に座って、旦那に隠す気なく堂々とイチャつく始末。
なんと政治家は時期総理大臣候補。
⑥精神科医
この状況下で人がどういう言動をするかに興味津々。
⑦宇宙生物学者
今後の展開に都合がよすぎる人物。
⑧ベトナム戦争で旦那を亡くしたアメリカ人女性
幾度と戦争のトラウマが蘇る。
叫び声担当。
⑨一般人男性
後に時限爆弾をもっていた自殺志願者だと判明。
⑩テロリスト
ハイジャック犯が逃亡し、機内から見えたUFOに遭遇。
そして憑りつかれる。
憑りつかれると額が縦にパカっと割れるらしい。
私はこういう特撮が大好物である。
このアイディアは、共同脚本を務めた高久進(たかく すすむ)が提案した。
フレドリック・ブラウンのSF小説『73光年の妖怪』を元にしているという。
彼は、『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975-1977)を始めとする多くのスーパー戦隊シリーズで脚本を務めた。
私の大好きな『忍者戦隊カクレンジャー』(1994-1995)でも、いくつものエピソードで脚本を務めているではないか。
妖怪は潜在的に好きだと思っていたけれど、こういった頃の記憶が未だに残っているからなのだろうなぁ。
彼はどういう攻撃をするのかというと、ただただ血を吸うのだ。
しかし吸っているチュパチュパ感もなければ、吸った後に口に血も着いていないので、吸っているようには見えない。
果たしてUFOに乗っているのは吸血鬼なのだろうか。
ところで本作は『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(1956)の邦画版といった位置づけだろうか。
後に3度《『SF/ボディ・スナッチャー』(1978)、『ボディ・スナッチャーズ』(1993)、『インベージョン』(2007)》リメイクされるアメリカの古典的SF映画である。
内容はいわゆる寄生映画。
同じジャンルで言えば、ジョン・W・キャンベルによる1938年の短編SF小説『影が行く』を映画化した『遊星よりの物体X』(1951)も忘れてはならない。
『吸血鬼ゴケミドロ』では、憑りつかれて用無しになった者は灰となって消える。
機内では生き残る方法を巡って口論に。
それぞれの人間性が露わになるのも寄生パニック映画の見どころの一つ。
その時に嫌な奴は必ず報いを受ける。
寄生生物は「ゴケミドロ」という名前らしい。
奴らはUFOから宇宙人風な日本語で語りかけてくる。
「我々は人類を支配しに来た」
時限爆弾を持ち込んだ者の正体も明らかになったが、彼はゴケに立ち向かった際に自爆してしまう。
結果、ゴケとの戦いで生き残った者は、男性パイロットと女性キャビンアテンダントのみ。
本編は84分しかないので、見せ場の連続でテンポが良く気持ちがいいですね。
憑りつかれたハイジャック犯が力尽きた時、ゴケミドロは身体から離脱を図った。
そして他の人体を標的にするのだった。
そんな中、日本各地はすでにゴケミドロの侵略を受けていた。
ゴケミドロの勝利。
人類が敗北するという終末を感じさせるエンディング。
人類誕生の起源なんてわかっていないのだから、我々の祖先が地球という惑星を侵略していた可能性もある。
人間がいるという不思議を考えると何でもあり得ますよ。
いつか元の住人の祖先が取り戻しに来るかもしれない。
しかし『吸血鬼ゴケミドロ』に言える唯一のことは、『復活の日』(1980)のような“希望”は存在しない。
我々人類は負けたのだ。
明日自慢できるトリビア
②「ゴケミドロ」の名の由来は、パイロットフィルムを制作したうしおそうじが京都でよく立ち寄るという「西芳寺」(苔寺=こけでら)と、「個人的に興味があった」という「深泥池」(みどろいけ)から着想した造語で、当初は「コケミドロ」としたが、興行で「こける」は禁句なので、濁点を着けて「ゴケミドロ」としたものである。
一方、松竹映画として公開される際には、松竹宣伝課によって「吸血鬼ゴケミドロとは何か?」と題し、「『ゴ・ケミ・ドロ』とは、三つの言葉が合成されて出来た言葉」とする説明文が各種宣材に添えられた。
こちらの文ではうしおの命名から大きく設定を拡げ、「ゴ」は「キリスト処刑で有名なゴルゴダの丘から採った、頭蓋骨を意味する言葉」で、「ケミ」は「ケミカルつまり、科学的処置を受けたという意味の略」、「ドロ」は「アンドロイドから採った言葉」としており、「SFの世界で宇宙の天体QXに生息する頭骨だけが異常に発達した“人間もどき”が特殊の科学的処置の洗礼を浴びて、水銀状の知性体に化したものが、このゴケミドロの正体なのです」「この水銀状の血を吸って生きる高等生物は、彼らの食糧(血)が減少したため、新たな食糧源を地球に求めてやって来た」と説明している。