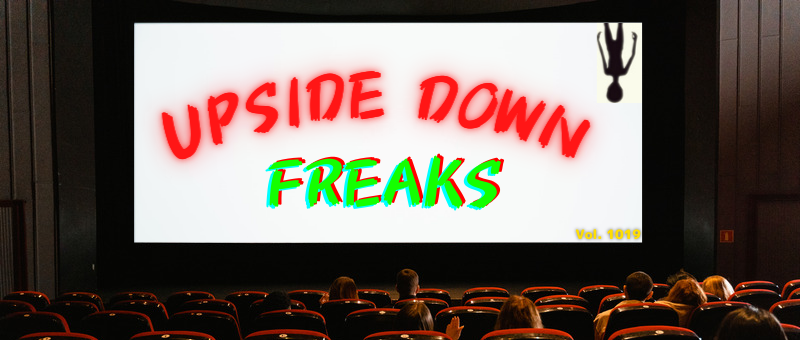野性的演出に圧巻であります
猛獣大脱走
三行粗筋
ほのぼの感想あるいは解説
監督のフランコ・E・プロスペリは、いわゆる問題作として有名なモキュメンタリー映画『世界残酷物語』(1962)でヤコペッティ監督と共同で監督を務めた人物である。
この経験は『猛獣大脱走』でおおいに生かされているに違いない。
説得力のある画作りを構築するという点で。
本物の動物を使う、それは命がけである。
とはいえ命がけ映画として名高い『ロアー』(1981)のように観ていて心配になるほどではない。
あちらは人が死ぬ一歩手前が永遠と続く作品であるため血の気が引く。
150頭ほどのライオンが撮影に参加し、象も登場する。
彼らを飼い馴らすことは出来ず、出演者とスタッフの多くが負傷する事態となった。
そんな動物を使ってでも表現したい映像があるのです。
『ベスト・キッド』がアメリカで公開された1984年、イタリアでは『猛獣大脱走』が公開されていたのだ。
『猛獣大脱走』の撮影中には3人の動物調教師が常に配置されて、彼らは動物たちが暴れた時に対処するべく麻酔銃を所持していたという。
冒頭に大量発生するネズミのシーンは『ウイラード』(1971)、その続編『ベン』(1972)を彷彿とさせる。
数は圧倒的にあちらの方が多いので可愛いもんです。
ちなみに『猛獣大脱走』のネズミたちは白色だったため、黒く塗る必要があったとIMDbには記載されている。
白い方が不気味にも感じる気はしますが、街中に実験用の白いネズミが溢れかえるのは違和感ありますよね。
本作の見どころは、やはり動物の本来の姿を普段いるはずのない街中で見れること。
特にチーターが車に乗りこんだ女性に目をつけて、その車が走り出すと追いかけ始め、気持ちいいくらいに道路を駆け抜ける姿は圧巻であります。
これぞ映画でしか見られない映像。
さらに、動物愛護団体による抗議の対象となってしまうが故に、映画の中ではなかなか見ることのない動物である象を何頭か使ったシーン。
さすがに言うことを聞いてくれない時もあるのであろう、そういう時には極端なクローズアップを多用した撮影で臨場感と迫力を演出してくれる。
ホッキョクグマも登場するのですが、学校内で歩いている動きが何だか人間ぽかったのでさすがに人が入っているのだろうかと思ったが、本作で登場する動物は全て本物だというのだから驚くばかり。
いい演技をしているホッキョクグマを疑ったことを猛省します。
終盤は急に趣旨が変わり思わず笑ってしまった。
研究所だったか工場だったか、そこから事故で流出した化学薬品の入った水を飲んでしまったことが“猛獣大暴走”の原因だったのだ。
「動物…それは人間も含まれるのだ」という恐怖をラストに突き付けられる。
子供たちが我を失い、まるでジョン・カーペンターの『光る眼』(1995)のように大人に襲いかかるのであった。
劇中では子供だけであったが、このあと大人も次第に狂っていくのであろうか期待の余地を残してエンディングを迎える。
もはやそうなったらジョージ・A・ロメロの『ザ・クレイジーズ』(1973)ではないか!
一言教訓
明日自慢できるトリビア
①出演者のアントニオ・ディ・レオは、ホッキョクグマが振るった足に危うく首を撥ねられるところだったが、かろうじて彼の頭を空かした。
②フランコ・プロスペリ監督は象と空港滑走路のシーンを撮影中に、1頭の象に足を踏まれている。
③動物の調教を担当したジャンカルロ・トリベルティは、地下鉄の中でトラに襲われて殺される男の役でカメオ出演している。
④地下鉄トンネルでのトラとのシーンは、午前1時から3時に撮影された。さらにそのトラは地下鉄の駅内で実際に逃走してしまい、電車の天井に上がるシーンの前にトイレに隠れてしまったそう。そのため地下鉄従業員はトラが捕まるまで駅に入ることを阻止された。